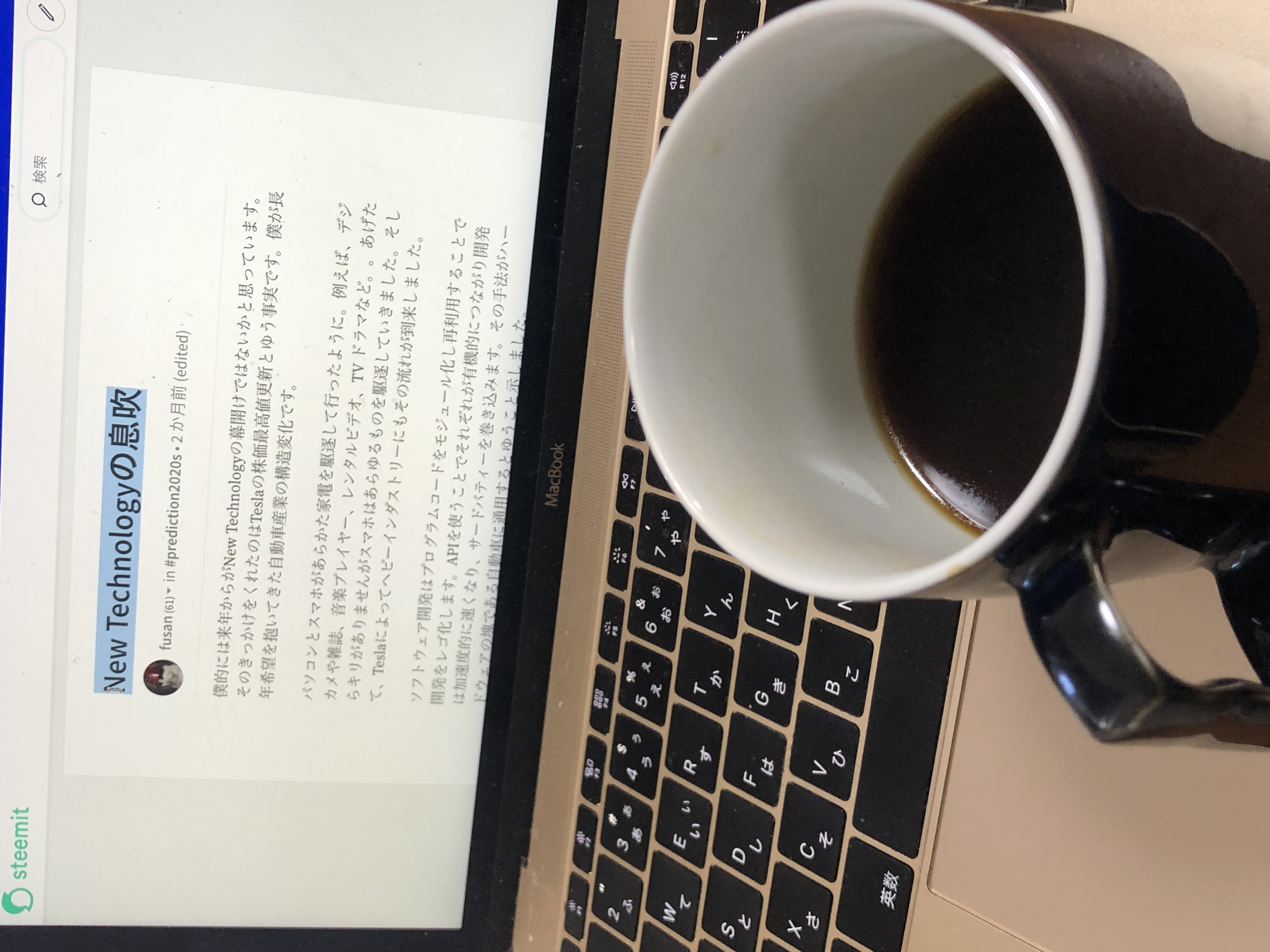最近、 @fusan の影響で、易経について学んでいます。
とくに太極図の考え方は、世の中を俯瞰するのに役立っていますが、昨今のコロナ騒動後の未来も、なんとなく予想できますね。
やっぱり、「学ぶことは、本質的に楽しいことだ!」と改めて感じます。
さて、そんな中「そういえば食べ物とかも、陰陽で分けていたよな・・・」と思い出しました。
そこで今回は、太極図(陰陽)の視点から、コーヒーについて眺めていきたいと思います。
1.前提 〜陰陽とは?〜
一言で言うと、
・陰は、マイナス ・陽は、プラス
ということですね。
具体的な事象だと、「冬ー夏」や「夜ー昼」などですが、単純な二元論でなく、どちらにも反対の性質を含んでいるという東洋思想がベースにあります。
さて、これを食品にあてはめてみると、
・陰性食品は体を緩めて、体から熱を逃がす ・陽性食品はからだを引き締め、体に熱を留める
このような原則があります。
もう少し、細かいところだと
・陰性食品:植物性、油、カリウム ・陽性食品:動物性、塩、ナトリウム
こういった、基準もあるみたいです。
代表的なところだと
・陰性食品:砂糖、牛乳、米 ・陽性食品:肉、魚、卵
こんな感じで、分類がされています。
2.陰陽から見たコーヒー
結論から言うと、コーヒーは「陰性食品」に分類されます。
「陰性食品は体を緩めて、体から熱を逃がす」ということでしたが、コーヒーには利尿作用があります。
これは、体から熱を逃がすということですが、これはコーヒー中の成分に「カリウムやカフェイン」が含まれているからですね。
「カフェイン=コーヒー」というイメージはとても強いですが、品種によって含有量が異なるようです。
アラビカ種よりロブスタ種の方が、倍近くの含有量があるそうです。
(ちなみに、カリウムの含有量はそこまで差がないみたいです)
またコーヒーは、様々な嗜好品の中でも、「脂質」を比較的多く含有している点でも特徴的です。
コーヒー以外だと、チョコレートが該当しますが、チョコレートは酸味が少ないですね。
「脂質がありながら、酸味もある」嗜好品は、実はコーヒーくらいしかないのです。
この視点から見ると、脂質が含まれているのも、陰性食品の特徴になりますね。
昨今のスペシャルティコーヒーは、その分類がワインのように多岐に渡ってきています。
なので、陰性食品の中でも、さらに陰陽のグラデーションが、産地ごとにありそうな予感がします。
個人的には、
「陰性」← インドネシア ケニア ガテマラ →「陽性」
こんなイメージ(仮説)を持っています。
3.まとめ
陰陽の考え方は、物事の本質を捉えるのに、とても適したものの一つだと思います。
コーヒーの最先端は「コーヒーサイエンス」とも言われていますが、太極を思い起こしながら、あれこれ考えながら飲むコーヒーも、独自路線なのかなと感じています。
もちろん、ふーさんのブログ記事を読みながら飲むコーヒーも、これまた贅沢な一杯なのですよ!